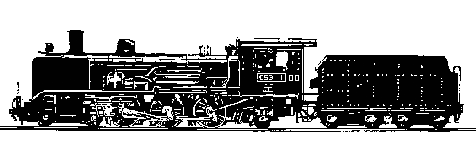
続:ユニバーサル・ジョイント
- いで爺

2025/12/09 (Tue) 05:58:52
 キハ35のユニバーサル・ジョイントの補強だけど...4両すべての補強は終わった。
キハ35のユニバーサル・ジョイントの補強だけど...4両すべての補強は終わった。
球が付いている方は4点支持なので、強度があるだろう。
...が、爪の方は2点支持なので破断する可能性が高いと思う。
なので、1両につき2ヵ所の爪の部分を銅パイプで補強してみた。
16番(HO)では、このタイプのユニバーサル・ジョイントが使えると思うけど...OJは重量があるので、ちょっと無理があるのではないだろうか。
これらの製品は、セッテや熊田貿易が発売していたけど、経年劣化で同じ事が起こるであろう。
所持している皆さんは、如何するのかなア~。
知恵と意地 - いで爺
2025/12/08 (Mon) 11:02:34
 ユニバーサル・ジョイントの爪が、破断したキハ35。
ユニバーサル・ジョイントの爪が、破断したキハ35。
意地で「直すぞオ~」...と、今まで培ってきた知恵でユニバーサル・ジョイントを修復したよ。
強度的に弱い部分を銅パイプで補強してみた。
その前に線路上をくまなく探して、破断した小さな爪を見つけるのが大変だった。
先ず、破断した爪を接着してから、ヤスリで形を整えて...銅パイプを被せてから、銅パイプに接着剤を流し込んでみた。
Re: 知恵と意地 - いで爺
2025/12/08 (Mon) 11:24:03
 はい、ユニバーサル・ジョイントを本体に取り付けて...首振り角度もバッチリ!! 修理完了。
はい、ユニバーサル・ジョイントを本体に取り付けて...首振り角度もバッチリ!! 修理完了。
銅パイプで確り補強したので、暫くはもつと思うんだけど...
破断した爪の部分は見るからに弱そうなので、残る3両も同じく銅パイプで補強する事にした。
経年劣化が進むと...
①プラスチックは「折れる・破断・割れる」
②ダイカストも「折れる・破断・割れる」
③真鍮は「折れる・破断・割れる」事はないけど、半田付けが外れる。
何れにしても車両は、年数が経てば何らかの形で壊れるけど...できる事ならば予防保全をしておきたい。
それと何事にも銅パイプを多用しているけど、加工がし易いので重宝する材料かなア~。
キハ35が壊れた - いで爺
2025/12/08 (Mon) 05:56:12
 昨日プログラミングして、やっと4両編成になったキハ35なんだけど...
昨日プログラミングして、やっと4両編成になったキハ35なんだけど...
最初に委託品で購入した、DC仕様だった2両目の車両が壊れた。
ユニバーサル・ジョイントの破断!!
以前から爪の部分が弱弱しいと思っていたんだけど...やっぱりか。
10年くらい前の製品で韓国製なので、部品もある筈がない。
手持ちの16番(HO)のユニバーサル・ジョイントで、手当てしようと考えたけど、首振り角度が小さくて使えないよ。
如何しよう!!
無ければ作るしかないんだけど、どうすれば良いのかなあア~。
他の車両も何れ同じ事になると思うので、折れない様に対策をする必要があるなア~。












